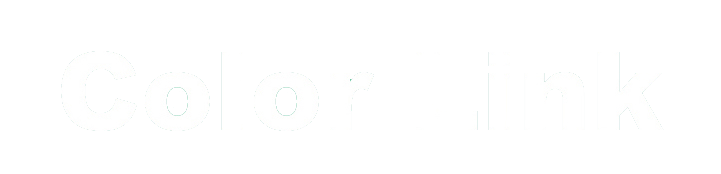江崎泰子(「色彩学校」主任講師)
現代の「アマビエ」から江戸時代の「赤絵」まで。人々は感染症を予防し、万が一罹っても軽くすむようにという願いを、「絵」に込めたというお話を紹介します。
写して広まったアマビエの絵
新型コロナウィルスの感染拡大にともなって、この春頃から「アマビエ」という妖怪モチーフが流行しています。人魚のような不思議なキャラクター、目にしたことのある人も多いでしょう。最初は、「疫病退散」祈願のシンボルとして神社のご朱印などに用いられていたのが、いろいろな人が独自のアマビエを描くようになり、今や厚生労働省のアイコン、ぬいぐるみやお菓子まで作られて、感染予防のお守り的シンボルとなっています。
-s.png)
▲江戸時代後期に描かれたアマビエのオリジナル画
もともとは江戸時代後期に肥後(熊本県)の海に出現したとされ、目撃した役人の記録として絵とともに瓦版に残されていたもの。それによると、豊作や疫病を予言し、「私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ」と言い渡して消えたと言います。
それにならってか、現在はネットでも自分の描いたアマビエを「写して人に見せるように」とコメントした作品が掲載されていたりします。人ってやはり願いやイメージを目に見える形にすることで、そこにより強く思を込めることができるのですね。

▲現代のアマビエ。多くの人が描いて広がっている。
エゴン・シーレも広重も感染症で亡くなった
そんなことを思いつつ、この連載も今回はアートと疫病(感染症)の関係について触れてみたいと思います。
日本でも諸外国でも、人類はこれまで繰り返しさまざまな感染症の脅威にさらされてきました。古今東西の画家はおおむね長生きとは言え、感染を免れるわけではありません。
知られているところでは、エゴン・シーレが当時ヨーロッパで猛威をふるったスペイン風邪で命を落としていますし、日本では浮世絵師・安藤広重が幕末に大流行したコレラに罹患して亡くなっています。

▲エゴン・シーレ『死と乙女』(1915年 ウィーン、オーストリア・ギャラリー)
この幕末の頃の日本は、開国や倒幕を巡って動乱期にあっただけではなく、安政の大地震(1855)が起き、江戸市中が大火事に見舞われ(1858)、さらに1862年には麻疹(はしか)の爆発的な流行が起こります。まさに震災や自然災害、感染症が度重なる現代日本のようです。
今は、麻疹といえば子どもが罹る病気。それもワクチンによって軽症で済むという認識でしょうが、当時は大人も感染し死に至る流行り病でした。きわめて感染力の高いウィルスが、飛沫や接触によって人から人へ感染し、高熱や咳、発疹が続いたあとで、合併症などによって多数の死者が出たのです。
この特徴、まるでコロナ?と思うほどですが、もっと恐ろしくて1862年の6月から8月までの死亡者数は、江戸市中だけで約1万5千人(現在の東京都のコロナウィルス感染死者数は2月~7月7日までの合計で325人)。しかも、この流行は江戸時代を通して14回繰り返されたという記録が残っています。(『江戸の流行り病』鈴木則子著・吉川弘文館より)

▲『江戸の流行り病』鈴木則子著。表紙は、江戸時代の麻疹絵。麻疹を無事退散させようという祈りをこめて描かれている。
隔離、店舗の営業自粛、貧民救済……、
今とほぼ同じ江戸時代の対策
当時の人々は、どうやってこうした感染症とつき合い、乗り越えてきたのでしょう?
もちろんこの時代の日本人には、ウィルスや細菌によって病気が引き起こされるという認識はまだありませんでした。長年の経験から得た知恵で病に立ち向かうしかなかったわけですが、感染症対策は今とさほど変わりません。
罹患した人の隔離に加え、食べ物屋、風呂屋、髪結い床(美容院)、遊郭(夜の街関連)や芝居小屋(エンタメ)などの営業自粛や客足の減少。病気を悪化させない食べ物や生活の仕方などのガイドも数多く出版されていました。また、働けなくなった貧民への救済も施されていました。
感染したら、病人の周りをすべて赤づくしに
そんな中、病気平癒を願う当時の習慣の1つとして広く行われていたのが、“赤信仰”でした。
ここでようやく江戸時代のアートセラピーとも言える話に入るわけですが、江戸時代を通して恐れられていたもう1つの感染症である疱瘡の場合はとくに、病人の周囲をすべて赤づくしにすることで重症化しなくて済むと信じられていました。
医療の歴史に詳しい北里大学名誉教授の立川昭二氏によると、「病人と看病人の衣類はもとより、寝具から調度、玩具に至るまで、すべて赤色のものを用いた。病室の入り口には紅紙の幕をたらし、(中略)紅餅、紅団子、紅小豆飯、赤鯛を供える」といったことを、将軍家から長屋の住人まで誰もが熱心に取り組んでいたようです。
また、病気を退治するヒーローや神様などが赤一色で描かれた「赤絵」が盛んに刷られ、病室の壁に貼られていました。簡単なストーリー仕立ての「紅絵本」もあり、子ども向けのお見舞いなどに用いられていたといいます。

▲疱瘡除けのために描かれたといわれる葛飾北斎の「鍾馗(しょうき)図」。朱一色を使った肉筆画で、鍾馗などの強いヒーローは疫病退散の力があると信じられていた。(すみだ美術館蔵)

▲疱瘡絵(鯛車)歌川芳虎画(武雄市蔵)
色に治癒効果があると信じられていたわけ
こうした赤信仰の背景には何があったのでしょう?
昔から太陽や火、血の色である赤が、魔除けや呪術的なパワーをもつ色として特別視されてきたことがひとつ。加えて、赤の顔料であるベンガラや朱の一部が不老長寿の妙薬として珍重されてきたこと、「赤絵」「紅絵本」の刷りに用いられていた紅花に血を清める効果があることなど含めて(「Health」参照)、色彩がもつ薬効を期待してのことだったのではないでしょうか。
また立川氏は「赤い色は網膜を通して中枢神経を刺激し、おそらく交感神経を興奮させ、脳下垂体を介して副腎皮質から抗炎症ホルモンを分泌させる可能性が考えられ、また交換神経が刺激されると、代謝や細胞が活性化されることになり、免疫能力を高めることがあり得るとも考えられる」と、医学的見解を述べられています。(『江戸 老いの文化』筑摩書房より)
そこにあえて私見をつけ加えるなら、病床に貼られた赤絵を毎日見ることで、ヒーローや神様が病気を撃退してくれるという一種のイメージ療法となり、治癒への後押しになったのではないかと推測できます。
そして何より子どもの場合は、普段は忙しい親が枕元に寄り添い紅絵本を読み聞かせてくれる、その親密な時間こそが内なる癒しの力を高めてくれたのではないでしょうか。
そんな意味で、江戸の赤色セラピーは決して迷信や俗説としてだけでは片づけられない、病気を乗り切る暮らしの知恵だったように思います。
あなたもコロナが心配なら、赤一色で絵を描いてパワーを高めてみてはいかがでしょうか?!
江崎 泰子(えざき やすこ)
「色彩学校」主任講師
長年に渡り、日本の色や美術を研究。和の文化や歴史、画家の人生に心理的な視点からアプローチしている。『事典・色彩自由自在』では伝統色名の解説を担当する一方、不定期で「日本文化と伝統色」の講座を開催。日常的にも好きな着物、歌舞伎、浮世絵などを楽しんでいる。