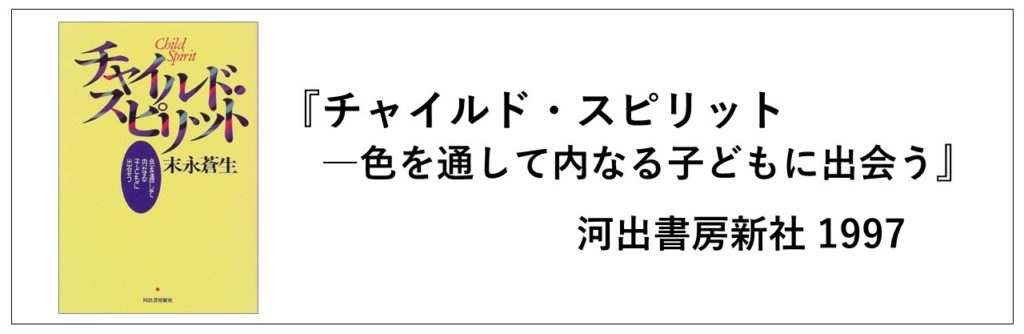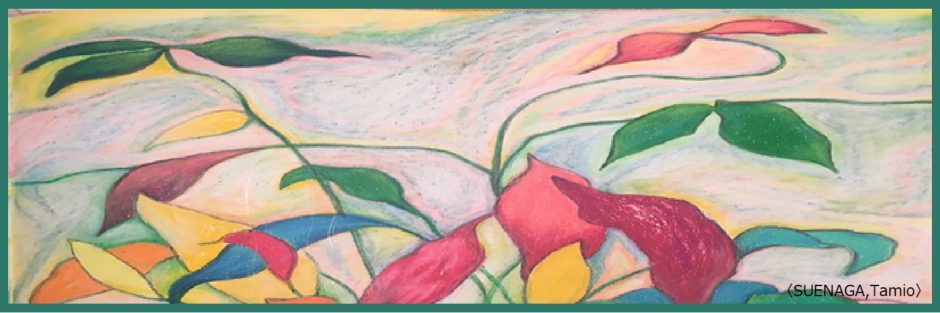愉しい色、自由なこころ
末永蒼生が長年に渡り思考してきた色と心についての珠玉の言葉を紹介していきます。
1988年出版の伝説の名著『色彩自由自在』から始まって、30冊以上の著書やエッセイの中から、今だからこそ伝えたいセンテンスを選び、定期的にアップ。
人間と色の関わり、セラピーとは何か、アートのもつ力……などについて語る、研究者ならではの鋭く本質的な言葉や、五感を刺激してくれる美しい言葉は、きっとあなたの心と思考を開いてくれるでしょう。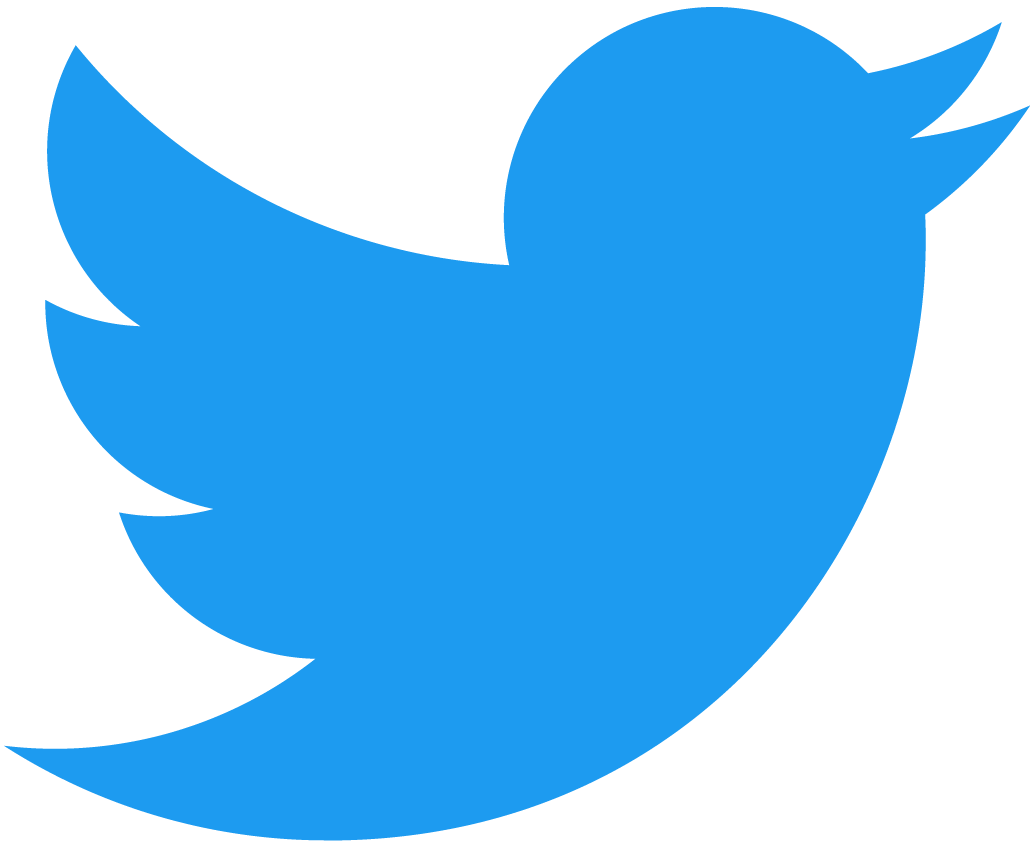 Twitter でも随時更新中!
Twitter でも随時更新中!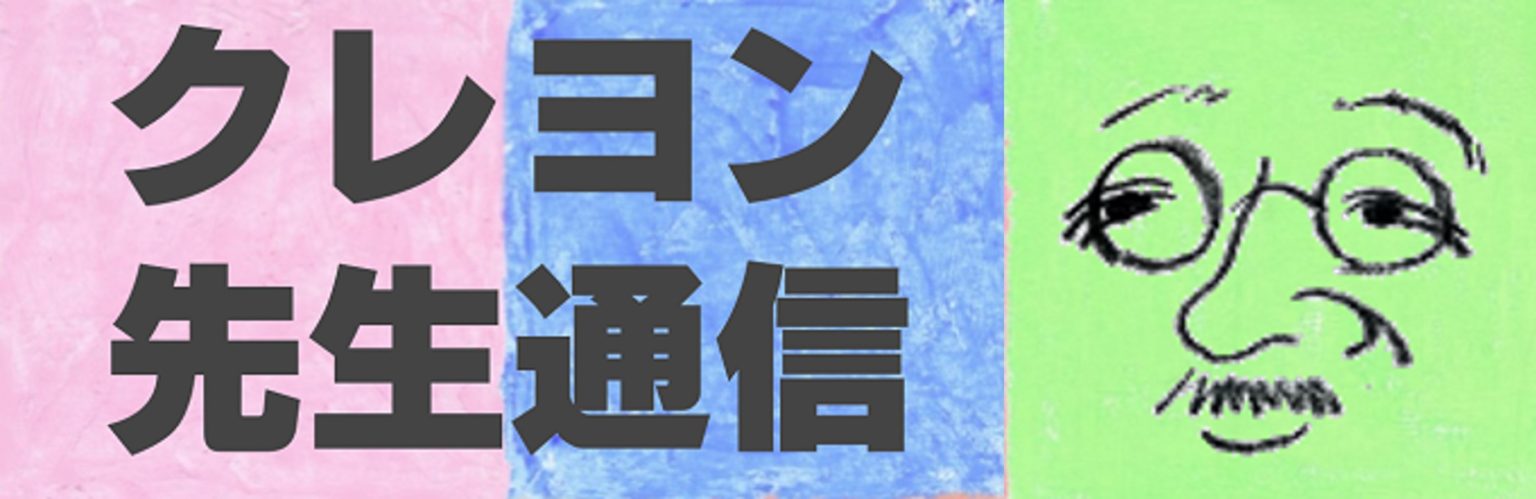
色彩の意味
赤の心理
●世界各地の古代文明、特に死者を埋葬した聖域に、赤が施される例が多いのはなぜなのか。 火の色、血の色である赤、つまり命の象徴である赤と、死の恐怖を越えようとした古代人の祈りが結びついたのではないだろうか。(『色彩心理の世界』より)
●世恐怖と闘って生きようとする人間のエネルギーは凄絶だ。しかし、その瞬間、人は内側に流れる血潮と呼応して赤という色に目覚めるのにちがいない(『色彩心理の世界』より)
黄の心理
●「黄色は光にもっとも近い色である」と言ったのは文豪ゲーテであるが、それは心理状態にも言えることなのだ。黄色という明るい色が欲しくなる時、その人の心は光の明るさや暖かさを求めている(『色彩心理の世界』より)
●「椅子とベッドはクローム・イエロー、枕とシーツは薄い緑がかったレモン色……、絶対的な休息を表現したかった」とゴッホはゴーギャンに書き送った。実際には二人の共同生活はゴッホの耳切り事件で破綻。“黄色い部屋”の絵は人との幸せを“静止画像”として永遠に刻んだ作品だったのかもしれない(『色彩心理の世界』より)
緑の心理
●地上に最初に登場した色が緑色だったはずだ。生物が上陸する前、まず苔やシダ類など植物の祖先たちが海辺から這い出し、やがてこの地球に酸素を生産していった。そして、花が咲き、虫や動物などが彩り豊かな生命世界が広がった。神がこの地上に与えた最初の 一筆が緑色だったのだ(『色彩心理の世界』より)
●利休は一服の茶を飲む行為が人に及ぼす力を知り尽くしていたのだろう。静寂の中に響く茶を点てる音、掌に触れる茶碗の肌触り、目に入る深い緑色、香りと味覚、そして一服へと向かう呼吸。……中でも、その緑色は視覚を通してのカラーセラピーの役を大いに果た したにちがいない(『色彩心理の世界』より)
青の心理
●青という色は彼岸と此岸を超越するシンボルとしてドイツロマン派のノヴァーリスの作品『青い花』を彩っている。……詩人の直感で、青という色が死と再生の象徴としてもっともふさわしいことをみごとに描き出している。私はそれだけでもこの小説が傑作だと感 じずにはいられない(『色彩心理の世界』より)
●色彩心理の調査をしてみても、青を好む時の心境として「絶望」「別れ」「孤独」などの言葉を挙げる一方、「自己探求」「浄化」「癒し」「内的成長」「解放感」「自立」「希望」「知的」などの言葉を挙げる人も多い。青色は、……大きく分けると“喪失感”と“再生”の双方の感情を反映するものとしてみることができる(『色彩心理の世界』より)
紫の心理
●私が子どもの頃はクレパスといってもほとんどが12色セットで紫色は入っていなかった。そのため、紫色が必要な時は必ず赤と青を混ぜ合わせて塗ったものだ。子どもながらに、赤と青という正反対の色の混色で生まれるこの色に不思議さを感じていたのである(『色彩心理の世界』より)
●「紫色を求める気持ちの中には、赤に代表される感情の昂揚と青に代表される沈滞した感情とを融合させ、バランスを取ろうとする欲求があるのではないかということである。紫色を美しく感じる感覚そのものが、回復しようとする生命力の現れなのだ」(『色彩心理の世界』より)
ピンクの心理
●かつてインドのアジャンタの石窟寺院を訪ねた時、……焼け付くような石の道をたどってやっとほの暗い寺院の中に入った途端、匂いたつような美しさを持つ菩薩の姿があった。そこに描かれた蓮華には二千年を経た今も淡いピンク色の面影が残っており、暑さを忘れ た記憶がある(『色彩心理の世界』より)
●子どもたちの絵を見る限りでは。男女の色彩嗜好に性差はない。男の子でもむろん赤やピンクをよく使う。……人は「男らしさ」「女らしさ」にあまり気を使わなくていいようなリラックスした場面でなら、少なくとも心理的には男にも女にもなれる、つまりジェンダーの交換が可能なのだ。(『色彩心理の世界』より)
無彩色の心理
●白の場合はよく「頭の中が真っ白になった」という言葉があるように、感情や意識が漂白されたような非日常的な状態に伴って選ばれる。これは良い悪いといったことではない。ショックで何も考えられないという状態もあるだろうし、初心に立ち返って無心な状態になるということだってあるだろう。(『色彩心理の世界』より)
●人間は精神的余裕を奪われた時、心の中に他の彩りを思い浮かべることが難しくなる。……逆に言えば、日頃、身の周りにある色彩というものがいかに心理的な安心感を与えているかということを示している。まさにピカソが語ったように、「色彩はある種の救いを意 味してしまう」のである。(『色彩心理の世界』より)
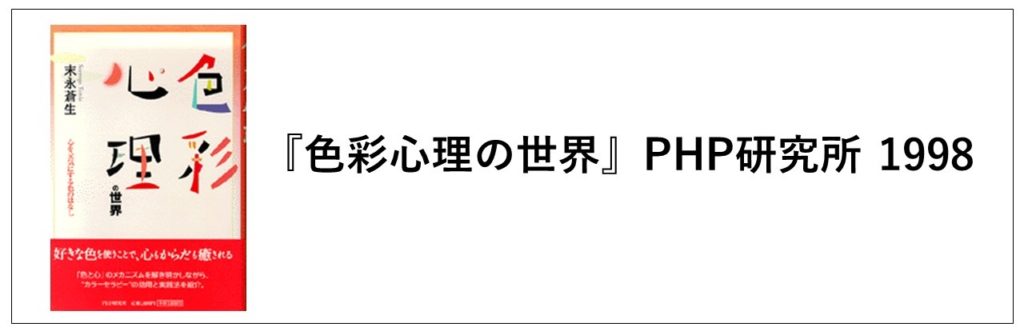
色と心
●色の世界とは、その波長のもつ普遍的な作用と個人的な記憶とが複雑に入りまじった、ダイナミックな領域である。
色は、まさに生きている。生きて、人間とともに呼吸している。そのダイナミズムに魅了されて、僕は20年以上も色彩の仕事にかかわってきた。(『色彩自由自在』より)
●心を語り、心を開くという意味では、色彩表現は言葉による会話以上に、すばらしいコミュニケーションを可能にしてくれる。
考えてみれば、人間にとって色は言葉以前の、生命と直結した〝もう1つのことば“だったはずである。(『色彩自由自在』より)
●ある特定の色を「美しい」とか「好き」と感じるのは、わたしたちの心身が、その時まさにその色の波長を必要とし、同調していることだといえる。
当然、わたしたちの心身が常に変化し続けているように、美しいと感じる色も、時間の移ろいのなかで変わっていく(『色彩自由自在』より)
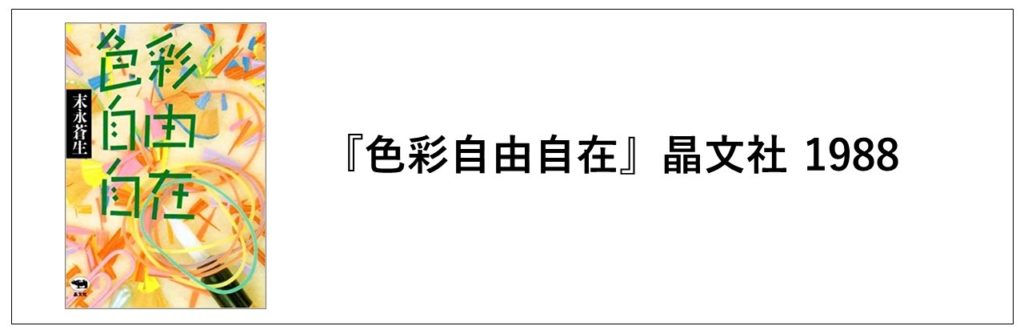
色の作用
●白や黒、あるいは赤や紫という極端な色は、瞬発的な突出したエネルギーを発生させるかもしれない。
しかし、人間は緊張のエネルギーだけでは生きていけない。柔軟なエネルギーを生み出してくれるような、微妙な中間色や微妙な段階をもった色彩環境が必要なのだ(『色彩自由自在』より)
色の表現
●色、あるいは絵というのは、寝ている間に見る夢のような、きわめて感覚的で流動的なものだ。好き嫌いはあっても、良い色、悪い色というのはない。そうすると、どの色を使っても、そのことによって非難されるとか、恥ずかしい思いをするということがない。それだけに自分の気持ちが現れやすいわけだ(『色彩自由自在』より)
無意識
●無意識に感じていることや言葉では言い出しにくい欲求というものが、社会的な価値体系に組み込まれていない、色という“もう1つの言葉”によって表現されやすくなる。そしてそれが、ありのままの自分を自覚するきっかけになるということでもある(『色彩自由自在』より)
子どもの絵
●太古の昔、ネイティブアメリカンやアボリジニなど先住の民たちが人類の幸福願って絵によるメッセージを残してくれたように、子どもたちの描く絵の中に、今、大切な何かが託されている。 (『チャイルドスピリット』より)
●(小学時代、空の色を黄色に塗り教師に注意された経験を思い出して)色を選ぶ時に、そこにその子どもなりの感情や心理、想像が働いているという(絵の心理的な)見方は、教師のいいなりにはなりたくなかった私自身の気持ちを肯定することにつながったのだ。 (『チャイルドスピリット』より)