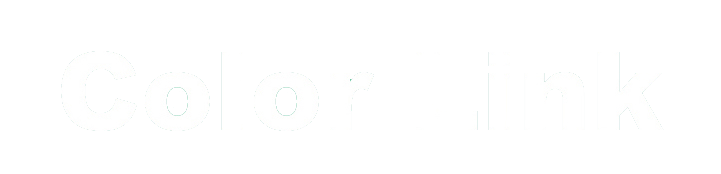長岡美江さん(滋賀県/染織家)
長岡美江さんは「色彩学校」3期の受講生で、その後しばらくスタッフとして仕事をしていましたが、あるとき突然、染織家の道を目指し京都へと旅立っていきました。
その後、地道な歩みを重ね、現在は琵琶湖にほど近い自宅アトリエで、天然の染料を使って糸を染め機で織って、着物を中心にした創作を行っています。
そして今年、その作品が高く評価され日本伝統工芸近畿展で賞を受賞!
そんな長岡さんに、これまでの道のりを振り返りつつ、自然の色の魅力や表現者としての自身について、さらに日本の手仕事や伝統工芸のこれからなど、多岐に渡るお話を綴ってもらいました。(取材・編集:江崎泰子)
自然の色に魅せられて染織の道へ
長岡 私が染織作家になった原点を考えると、今から30年ほど前の「色彩学校」3期で学んでいた時にまで遡ります。そこで草木染に初めて出会ったのが、日本の伝統色の課外授業での紅花染でした。
村上道太郎先生は波乱万丈の人生を経て草木染を独学、作品づくりと執筆活動をされていました。自然豊かな伊豆の山あいにあるアトリエに伺い、紅花を使った染色は楽しい体験でした。染めあがった淡い紅色は優しくそれでいてとても力強く、先生のいう「どこまでも人の心を吸い込んでくれる自然の色」です。また、花弁から黄色と紅色の二色が染まることの不思議さや、工業製品の絵の具ではなく自然そのものから色をとり出せることにも惹かれました。私の心の中で『もっと草木染をやってみたい』という気持ちが湧きあがったのです。

▲自然から染め出された色はどこまでも美しく澄んでいる。
その頃は、私(江崎)が主宰する日本の伝統色の勉強会で、様々なところに出向き貴重な体験をしましたね。素晴らしい先生方とも、たくさん出会いました。
長岡 あの頃の「色彩学校」は一見敏男先生の色彩の基礎知識にはじまり、末永蒼生先生の色彩心理、画家・斉藤祝子先生のシュタイナーのアートセラピーのワークショップなど本当に多彩でした。
染色家・吉岡幸雄先生には草木染の淡い色というイメージを覆して、鮮やかで華やかな色で奈良時代の伎楽の衣装や源氏物語の重ね色目の再現を見せいただきました。そして写真家・内藤忠行さんや舞台衣装アーティスト・毛利巨男さんなど多くのクリエーターの先生が熱心な講義を展開され、私はいつの間にか『表現することを生活の中心にしたい』と思うようになっていました。
仕事を辞めて染織の勉強を始めたのは、「色彩学校」での気づきがあったから
それにしても、東京の暮らしから突然一人で京都へと旅だったのには周囲も驚いたでしょう。当時の長岡さんを突き動かしていたものは何だったのでしょうか?
長岡 やりがいのある仕事を辞めて、突然京都のテキスタイルスクールで染織の勉強を始めた時、私は既に30歳を越えていたので、周りの友人からはとても驚かれました。それが出来たのは「色彩学校」での気づきがあったからで、それは心の中の無意識を色彩とともに旅するような体験でした。
そもそも「色彩学校」を受講した動機は『自分の感性が活かせる仕事がしたい』という思いからですが、今振り返ってみれば、20代の私はどこかで生き辛さを抱えていたように思います。
20代後半には身近な友人が次々と結婚して変わっていく中で、私は仕事が中途半端なまま、出口のない迷路にいるようで息苦しさが増していきました。
自分の心の癖や人に対する反応・行動パターンは何処から来るのか、その無意識の行動原因を日常生活の中で気づくことは難しいことです。「色彩学校」での色彩心理の講義やカラーヒストリー、ワークショップの経験は、心の中の無意識のかけらを少しずつ拾って行くような作業でした。その中で私の生き辛さは、子どもの頃の母親との関係が深く影響していることに気づきました。
母は思い込みが強く、子どもの性格やタイミングを考えないで自分がいいと思ったことをすぐに実行し、結果ちぐはぐになってしまうのです。例えば私はバレエが習いたかったのにピアノを習わされたり、猫が飼いたかったのに文鳥を飼ったり。小学校の高学年にラジオの英会話講座を聞かされた時はかえって英語に苦手意識を持ってしまいました。
もちろん母が好きだった分野ー美術や工芸・文学・仏像・映画など、私も好きになったことが沢山あります。でも子どもの頃の私は母にもっと気持ちを聞いて欲しかったのです。そうして私は無意識のうちに『人が何を望んでいるかをすぐに察してしまう』とか『人に頼らず何でも一人でやろうとする』という心の癖がついてしまい、本当の自分の気持ちを押し込めてしまっていることさえ分からなくなっていたのだと思います。
そんなことに気づいていったからこそ、「自分が心から望む人生を生きたい」「心の中にあふれる色を表現したい」という気持ちが強くなったのだと思います。

▲「心の中にあふれる色を表現したい」と、新たな自分の人生を見出した長岡さん。
試行錯誤の末、私の糸のパレットには色が溢れてきました
紅花や紫根、茜、藍など、日本人は古より自然の植物などから色をいただいてきましたが、実際、草木から染料を抽出し色を創りだすのは大変でしたか?
長岡 京都のテキスタイルスクールで染めや織りの基礎を3年間学んだ後、滋賀県に住むようになり自宅で創作活動を始めました。実際に着物のデザインを考え、糸を天然の材料を使って染めるようになって、しばらくすると私は美しい色を表現したくて草木染を始めたのに、染められる色数がとても限られてしまうことに気づかされ愕然としました。
枝・葉・実・根のどこに色素があるかは植物によって違いますが、どんな植物でも薄い茶色や黄色には染めることができます。しかし鮮やかな赤・青・黄色・紫が染まる植物や虫や貝等はとても限られています。しかも天然染料による染色は1+1=2とはいきません。例えば鮮やかなはっきりした色を染めたいと思っても、何度も染め重ねると色は鮮やかさを失い暗く濁った色になってしまうことがあります。だからこそ染色の作業は理科の実験のように計量・温度や時間の管理を正確にしなくてはならず、データをとることも大切です。
その後、試行錯誤の末、媒染を工夫することと染液の濃度を変えることで色数が増えていき、私の糸のパレットには段々と色が溢れていきました。

▲草木染に使う天然染料。左上からインド茜、藍、くるみ、左下は刈安、柘榴、コチニール。

▲長岡さんが染めた草木染の糸。赤から青、紫に至るまで豊かな色が並ぶ。
私が作品をつくる手順は、最初にテーマやイメージに添ったラフスケッチを何枚か描き、それからどの染料で何色に染めるか、どんな織り方にするか、全体の構成はどうするかを決め、糸量計算や染料計算ができる詳細なデザイン画を描きます。しかし一番苦心するのは、たて糸によこ糸を織り込んだ時、どんな表情になるか、色がどのように重なり合い響きあうかです。これはある程度の予測をするものの実際はやってみないと分りません。時にはデザインを最初から考え直さなければならないことになってしまうこともあります。糸に光沢があるかないか・太さの違い・織り組織・色の組み合わせ等々、ちょっとしたことで素敵になったり、野暮ったくなったりするのです。
そうして作れるのは、私の場合はデザインと作業に時間がかかってしまうので着物が1年に2枚くらい。染織は、本当に根気のいる作業なのです。
表現活動をしていく上で大切なのは、自分の感覚を信じること
今、長岡さんは工芸の世界でオリジナル作品を作り表現活動をされているわけですが、「表現」ということについて「色彩学校」での体験が何か役立ったことはありますか。
長岡 「色彩学校」では講義を聞くだけでなく、自分で色を表現する時間がたくさんあり、それをみんなと共有することが良かったと思います。その中でとても印象に残っている二色配色のレッスンがありました。『自然体』という言葉で配色をつくり発表した時、その色は本当に多岐にわたっていました。その元となったイメージも自分の生まれ育った土地の森と空の色の組み合わせだったり、日曜日の朝のリラックスした感じだったり様々です。配色が一人一人違っていて、そのどれもが素晴らしいと感じた時、自分の色の組み合わせも『自分らしさ』なのだからこれを大事にしようと強く思いました。

▲「望月」と題された長岡さんの紬織帯。四季や自然をテーマに作品を作ることが多く、そのイメージがそのままタイトルに。
「自分の感覚を信じる」これは何か表現活動をして行くうえでとても大切なことだと思います。多様性の時代のなかで一人一人の違いを愛おしく思い、自分自身の感覚も肯定できる、このような体験こそ本当に必要とされているのではないでしょうか。
何かを表現することが特別なことではなく、もっと身近で日常的なものになればいいと思います。それは楽しいと同時に自分や親しい人の新たな一面を知るキッカケになるからです。

▲現在は墨彩画クラスに参加され、協会員としても長いつき合いが続いている。
村西恵津先生の「和の講座・墨彩画」がコロナ禍でオンラインとなり地方に住んでいる私も受講することができるようになりました。墨や顔彩で描くことは楽しくまた難しいですが、新鮮で魅了されています。
そこで気づいたのは、上手く描こうと集中している時、息が止まり全身に力が入っていると絵が窮屈な感じになってしまい、逆に筆の勢いで大胆に描いた方がのびやかないい絵になることです。筆と墨は描き手の呼吸がダイレクトに表れるツールです。そしてこのことは機織りにも通じることだと思いました。織りは一つ一つの作業を正確に緻密にしなければならないため、一日の終わりには全身が凝り固まってひどい状態になります。そこで今は余分な力を入れずにリラックスして織ることを心がけています。
この度、日本伝統工芸近畿展で『松下幸之助記念賞』されましたね。賞をいただいたことで、改めて感じたことなどあれば聞かせてください。
長岡 受賞して感じたことは、着物という伝統工芸の作品であっても時代の空気を表したものが人の心に響くということです。
この着物のデザインを考えたのは、新型コロナウイルス感染症の拡大が始まった頃で、ともかくこの先の見えない日々の中、希望を感じる作品をつくりたいと切に思いました。最初のイメージは「扉」で、そのイメージを中心から右側と左側の色が違う片身替わりの着物で表現しようと決めました。
コロナ禍の不便や不自由が終わり、新しい時代へと扉が開かれる希望を、刻々と変化する夜明けの湖の景色に重ねました。後に『ColorLink』で末永先生が書かれていた『コロナ禍で子どもたちが画面を真中から二つに割った絵を描いている』という記事を読んで、人が無意識に同じことを感じ表現することを実感し感動しました。


▲日本伝統工芸近畿展で受賞した紬織の着物。作品タイトルは「明けの湖」。
天女の羽衣のような、心の翼が羽ばたくような着物を作ってみたい
日本だけではなく、今、世界中で伝統的な手仕事の世界が失われつつありますよね。後継者不足もあり、何十年、何百年と続いてきた技や知恵が引き継がれなくなっている。そんな中で、長岡さんはこれからどのように、どんな仕事をしていきたいですか。
長岡 私の仕事についていえば、着物がこれからどうなって行くかが憂慮されます。1990年代には日常生活の中で着物を愛用する人はいました。茶道を嗜む人の素敵な着物姿も見かけました。冠婚葬祭にはそれに相応しい黒留袖や喪の着物を多くの人が持っていました。しかし今では日常生活や人生の節目でさえも着物を着る機会は失われてしまいました。
この30年間の中で着物の需要が減り、その影響で材料の繭をつくる養蚕農家は激減し、繭から絹糸をつくる工場がなくなり、織物の加工に関わる工房は少なくなり、織るための道具をつくる職人も次々と廃業して行きました。
若い人たちにとっては、もはや着物は観光地でレンタルして、写真を撮るためだけのアイテムになっています。「簡単・便利・経済的」を追い求めて発展して行く社会の中では、「複雑・不便・高価」な着物が衰退していくのは当然の流れかもしれませんが。
今では染織だけでなく陶芸・木工・金工・ガラスあらゆる美術工芸が危機にさらされています。それならば工芸は単なる『もの』から『意識を変えるもの』へ進化して行かなければならないかもしれません。

▲長岡美江さんの展覧会にて。
日本では歴史的に襖や衝立に絵を描き、陶器や漆器に美を感じ愛でてきました。それは日本人の自然を身近に感じたい、自然の持つパワーを生活の中に取り入れたいという気持ちの表れであると思います。しかし今は、経済発展の名のもとに自然環境を破壊してきたツケが百年に一度という大規模な自然災害となって生活を脅かしています。人々はようやく「自然」や「環境」を振り返り、「持続可能な社会」を考え始めました。
美術工芸の創作の過程は、自然の素材を使い、その声を聞くことです。自然の摂理を知らなければ美しい作品は生まれません。自然の循環の中に人間もいることを強く感じさせる作品をつくることが出来れば、工芸の新しい価値が開けるのではないか。美しいものは人の心を動かす、それが自然と密接な関係にある工芸に託された重要な鍵ではないでしょうか。
自分の作品についていえば、抽象的なんですけど “天女の羽衣” のような着物をつくてみたいですね(笑)。日本の民話には必ず天女の羽衣が出てきますね。それを着るとパワーをもらって、変身するみたいな。なぜ衣なのか、着物に威力を感じるのは不思議ですよね。
なので、私も人にパワーを与えられる羽衣のような着物を作ってみたい、心の翼が羽ばたくような……。夢物語みたいですけど、そんなことを想っています。

▲「春雨」と題された絣織着物作品。天然染料ならではの柔らかな配色が美しい。